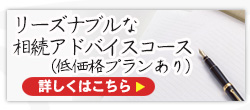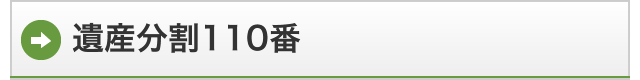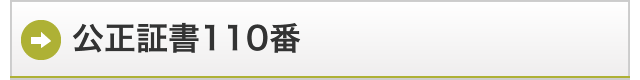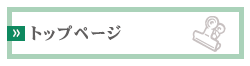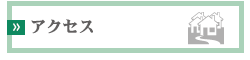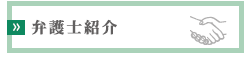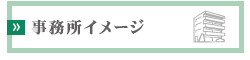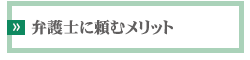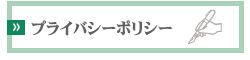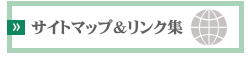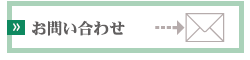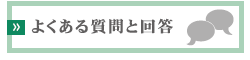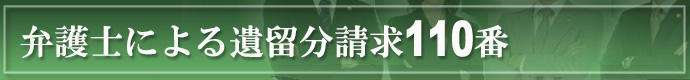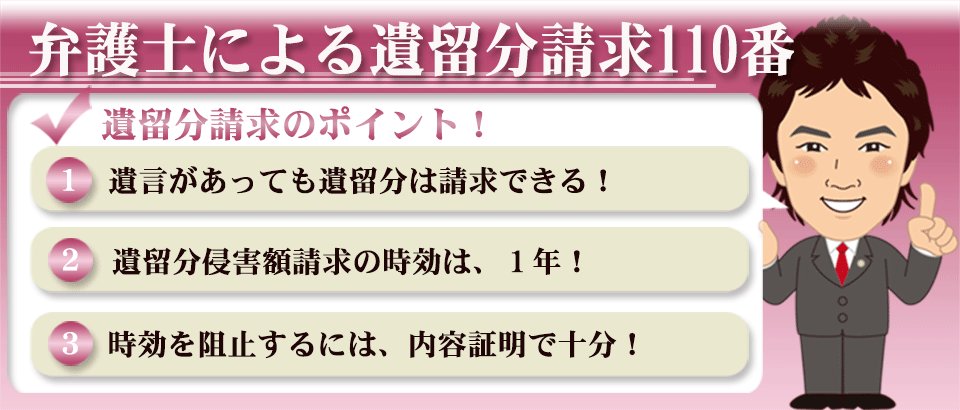
遺留分請求のプロが答えるQ&A~目次
第1「遺産分割の手続き全般」について
- 遺言で特定の相続人を完全に相続させないことってできるの?
- 被相続人が生前に贈与をしていた。この場合にも遺留分の適用はあるの?
- 遺留分とは?
- 遺留分は、どれくらい請求できるの?
- すべての相続人に遺留分があるの?
- 遺留分には例外はないの?
- 遺留分侵害額請求は、裁判でする必要があるの?
- 遺留分侵害額請求は、口頭で言えばいいの?
- 遺留分侵害額請求の意思表示をする書面には、何を書けばいいの?
- 遺留分には時効はあるの?
- 遺留分を侵害している場合、遺贈や贈与は無効になるの?
- 唯一の相続財産である不動産すべてを一人の相続人に相続させる旨の遺言が存在するが、他の相続人から遺贈遺留分侵害額請求をされた。どうなるの?
- 唯一の相続財産である不動産すべてを一人の相続人に相続させる旨の遺言が存在し、既に不動産を売却した。他の相続人から遺贈遺留分侵害額請求をされたらどうなるの?
- 遺留分は、放棄できるの?
- 遺留分を、放棄できるとしても、相続発生前に放棄できるの?
第1「遺留分について」
 遺言で特定の相続人を完全に相続させないことってできるの?
遺言で特定の相続人を完全に相続させないことってできるの?
いいえ、遺留分があります。
○ 被相続人(亡くなれた方)が「長男に全財産を相続させる」という遺言を残したとしても、他の相続人は、遺留分の範囲で相続権を主張することが可能です。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 被相続人が生前に贈与をしていた。この場合にも遺留分の適用はあるの?
被相続人が生前に贈与をしていた。この場合にも遺留分の適用はあるの?
はい、あります。
○ 民法では、相続開始から遡って1年以内にした贈与も遺留分算定の際の相続財産に含まれる旨、規定しております(1044条前段)。
○ また、相続開始から1年以上前の贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者を害することを知って贈与した場合は、同様に遺留分算定の際の相続財産に含める旨、規定しております(後段)。
「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。」(1043条)
「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」(民法1044条)
○ つまり、遺言による相続の場合だけではなく、生前贈与による場合も遺言同様に遺留分があります。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分とは?
遺留分とは?
○ 遺留分とは、遺言や生前贈与によっても害することのできない推定相続人のための権利です
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一(民法1042条)。
○ 遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることで、一定割合の権利を請求することができます。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分は、どれくらい請求できるの?
遺留分は、どれくらい請求できるの?
○ 遺留分侵害額請求の主張割合は、以下の通りです。
- 配偶者や子の遺留分は、法定相続分の2分の1
- 父母等の直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、法定相続分の3分の1
○ 例えば、父が死亡し遺産が1億2000万円で、相続人として長男、次男、三男の三人がいるとします。父が「すべての遺産を次男と三男で二等分させる」という遺言を残した場合、長男はいくら遺留分侵害額請求できるのでしょうか。
- まず、遺留分の基礎財産となるのは1億2000万円です。
- 次に、各人の遺留分の額は、基礎財産×法定相続分×2分の1となるので、 1億2000万円×3分の1×2分の1=2000万円となります。
- 長男の遺留分侵害額は、遺留分の額-遺産取得額となるので、 2000万円-0円=2000万円となります。
- よって、長男は、次男と三男に対し、各1000万円ずつを侵害額請求できることになります。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 すべての相続人に遺留分があるの?
すべての相続人に遺留分があるの?
 遺留分には例外はないの?
遺留分には例外はないの?
あります。
○ 中小企業の経営承継の円滑化の観点から、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、遺留分に関する民法の特例が定められております。
○ これにより、中小企業の代表者が会社の後継者である推定相続人の一部の者に自社株を贈与したり、後継者が相続した場合に、当該株式の一部又は全部について、その取得した価額を遺留分算定の際に加算しないことが可能になります。
具体的には、 事業承継110番へ
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分侵害額請求は、裁判でする必要があるの?
遺留分侵害額請求は、裁判でする必要があるの?
いいえ。
○ 遺留分侵害額請求は、意思表示で足りるので、必ずしも訴訟をする必要はありません。
○ 意思表示をした後に、協議をし、まとまらなければ調停の申立をするか訴訟提起をすることになります。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分侵害額請求は、口頭で言えばいいの?
遺留分侵害額請求は、口頭で言えばいいの?
いいえ。
○ 法律上、書面によることは要求されておりません。
○ しかし、実務では、意思表示をしたことを証拠化するために、内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をするのが通例です。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分侵害額請求の意思表示をする書面には、何を書けばいいの?
遺留分侵害額請求の意思表示をする書面には、何を書けばいいの?
○ 「遺留分の侵害額を請求する」旨の記載があれば足ります。
○ 最初の段階では、具体的な金額等まで特定する必要はありません。
○ もっとも、最終的には、具体的な侵害を立証しなければなりません。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分には時効はあるの?
遺留分には時効はあるの?
はい、あります。
○ 遺留分侵害額請求権は、相続開始および侵害すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、もしくは相続開始の時から10年以内に行使しなければなりません(民法1048条)。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分を侵害している場合、遺贈や贈与は無効になるの?
遺留分を侵害している場合、遺贈や贈与は無効になるの?
いいえ。
○ 遺留分を侵害する場合でも、その遺言や生前贈与が無効になるわけではありません。遺留分権利者は、その侵害された遺留分相当分の請求ができるだけであり、遺贈や贈与自体を無効にできるわけではないのです。
○ また、遺留分侵害額請求をされて初めて、その遺贈や生前贈与の一部が無効になります。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 唯一の相続財産である不動産すべてを一人の相続人に相続させる旨の遺言が存在するが、他の相続人から遺贈遺留分侵害額請求をされた。どうなるの?
唯一の相続財産である不動産すべてを一人の相続人に相続させる旨の遺言が存在するが、他の相続人から遺贈遺留分侵害額請求をされた。どうなるの?
○ 遺留分侵害額請求をされた場合、その遺留分の侵害の範囲で当然に遺贈や生前贈与は効力を失います。それに伴い、遺留分権利者は、その権利を取得します。
○ 遺留分減殺請求(旧制度)では、遺産に不動産がある場合は、受贈者又は受遺者は、遺留分権利者に対して、不動産の共有持分の移転登記手続きを請求することになっていました。しかし、新しい制度である「遺留分侵害額請求」では、不動産の権利そのものではなく、その権利の財産的な価値に応じた金銭を請求することができるようになりました。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 唯一の相続財産である不動産すべてを一人の相続人に相続させる旨の遺言が存在し、既に不動産を売却した。他の相続人から遺贈遺留分侵害額請求をされたらどうなるの?
唯一の相続財産である不動産すべてを一人の相続人に相続させる旨の遺言が存在し、既に不動産を売却した。他の相続人から遺贈遺留分侵害額請求をされたらどうなるの?
○ 目的物が第三者に譲渡された場合には、遺留分権利者は、原則、第三者に対しては、遺留分侵害額請求をすることはできません。
○ もっとも、遺留分権利者は、受贈者又は受遺者に対して、価額の弁償を請求できます。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分は、放棄できるの?
遺留分は、放棄できるの?
はい。
○ 遺留分権利者は、遺留分を放棄することができます。
○ 遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
 遺留分を、放棄できるとしても、相続発生前に放棄できるの?
遺留分を、放棄できるとしても、相続発生前に放棄できるの?
はい。
○遺留分権利者は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます(民法1043条1項)。
電話相談はできませんので、渋谷の事務所にご来所下さい。
○遺留分侵害額請求問題でお困りの方へ
|
~遺留分侵害額請求は、遺言書の作成や遺産分割協議の際に問題になることが多く、また、法律的な知識が必要とされます。遺留分侵害額請求でお悩みの場合には、専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
東京・渋谷駅徒歩5分にある弁護士9名が所属するウカイ&パートナーズ法律事務所では、遺留分侵害額請求のご依頼も承っております。遺留分侵害額請求に関するご依頼受けた場合には、内容証明等での請求のみならず、その後の調停や審判、裁判等のご対応が可能です。
ご要望の方は、フリーダイヤルもしくはメールにて弁護士との法律相談をご予約ください。
|
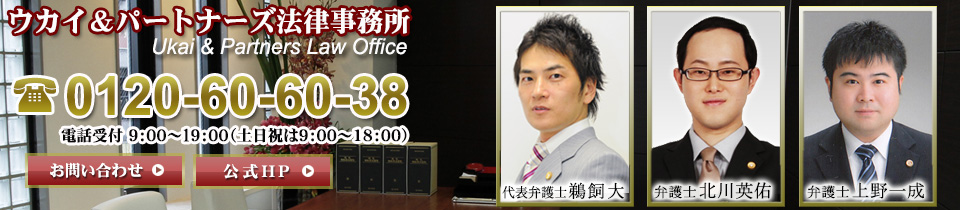
|
遺産相続弁護士110番トップ アクセス 弁護士紹介 事務所イメージ 弁護士に頼むメリット サイトマップ&リンク集 お問い合わせ よくある質問と回答 マスコミ出演 |
弁護士費用110番 遺産相続110番 遺言110番 遺産分割110番 借金相続110番 相続放棄110番 相続排除110番 |
遺留分110番 特別受益110番 寄与分110番 事業承継110番 後見110番 相続税110番 公正証書110番 |

|
 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-5 SK青山ビル8F TEL : 03(3463)5551 |